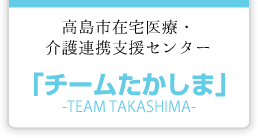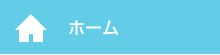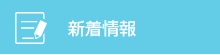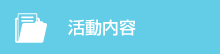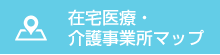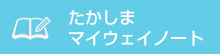新着情報
カテゴリー「報告」の記事
「多職種連携セミナー」「第160回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和8年2月14日(土) 午後3時~5時
場 所 今津サンブリッジホテル サンブリッジホール
内 容 講演と意見交換
座長 松本 道明先生 高島市医師会 会長
講演 「総合診療医の養成と在宅医療 ~竜王町で行っていること~」
講師 雨森 正記先生
医療法人滋賀家庭医療学センタ― 弓削メディカルクリニック 理事長
一般社団法人滋賀県医師会 理事
日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県支部 支部長
今回は、多職種連携セミナーとして、医療法人滋賀家庭医療センター・弓削メディカルクリニック 理事長の雨森正記先生をお招きし、「総合診療医の養成と在宅医療 ~竜王町で行っていること~」と題して、ご講演いただきました。
雨森先生は、竜王町に根を下ろして35年、人口11,000人のところで、地域に暮らす人々を総合的に診て支える医師を育てるため、自ら先陣を切って総合診療医の養成を行っておられます。
家庭医は、内科や小児科、皮膚科など各臓器に分かれた診療ではなく、患者の性別、年齢、臓器にとらわれない広く総合的な診療を行います。
生まれてから看取りまで地域のすべての方を対象として、診療や教育、予防、在宅医療、多職種や地域住民と協働し、その町で楽しく普通に暮らせるよう、質の高いかかりつけ医を目指して取り組まれています。行っておられることすべてが、医療を通したまちづくりとつながり、総合診療医・家庭医のグループ診療、在宅医療の多職種連携等を実現されています。そこで何が必要なのか、どうしたらできるのかを考え実践しておらます。
グループワークでは、事例をとおして多職種で活発な意見交換ができました。一緒に考えていくことやコミュニケーションの大切さも再認識できました。
高島市はいろいろな資源も少ないところですが、限られた中で工夫してみることや大切なことがなおざりになっていないか確認すること、事例をとおして各職種の理解を深めながら、話し合える機会をつくっていくこと等、一つひとつの取り組みが大切で、学びの多い良い機会をいただくことができました。教育の大切さ、こういった学べる機会があることも、もっと周知していきたいと思います。
そして、今後も各関係機関が役割を発揮し、さらに連携を深めていきたいと思います。



◆次回の予定 第161回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和8年3月5(木)14:00~15:15
会場:安曇川公民館 ふじのきホール
内容:話題提供 『「死」を「最高の記憶」へ変える連携のカタチ
―意思決定をグリーフケアへ繋げた葛藤の実践報告―』
話題提供者 リハビリ訪問看護ステーションWalk
代表 大森 健一氏
第159回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和8年1月15日(木) 午後2時~3時15分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「大津圏域と湖西圏域の連携の現状や課題および今後の展望など」
話題提供者 大津赤十字病院
副院長・患者支援センター 片倉 浩理 先生
医療社会事業課 兼 地域生活支援課 課長 梶原 英輝 氏
退院支援看護師 師長 森田 美砂 氏
今回は、大津赤十字病院よりゲストをお迎えして、大津赤十字病院の取り組みや紹介患者の状況、高島市との連携等についてご紹介いただき、意見交換を行いました。
大津赤十字病院は、70床の病床数を減らして602床となり、最新鋭の医療機器の導入や院内DXを推進して、医療の質や機能の充実を図り、地域との連携や救急と災害医療を強化されています。平均在院日数は年々減少し、令和6年度には10.7日となっています。
「紹介受診重点医療機関」として、一部外来完全予約制を導入し、効率的で質の高い外来医療の提供やラピッドドクターカーの導入を進め、救急医療体制の強化にも取り組まれています。またプロの医療人を目指して、人材育成やハラスメントの撲滅等にも積極的に取り組まれています。
令和6年度の医療圏域別の紹介割合では、大津市内が82%とほとんどを占め、次いで京都府内が5.3%、湖西圏域が4.6%となっています。令和7年4月から12月末までの高島市内からの紹介で、最も多いのは高島市民病院で307件、マキノ病院69件、今津病院 34件、他に市内の各開業医からも紹介があります。
大津赤十字病院から高島市内の病院への転院は経年でみると、高島市民病院へは少なくなり、今津病院の回復期リハビリ病棟への転院、マキノ病院へ緩和ケアが必要な方の転院もあります。
在院日数の短縮に向けて入院前支援に力を入れていて、看護師や薬剤師が情報把握して病棟につなぎ、手術の症例では日曜日の入院も増えてきているということです。
意見交換では、取り組みの苦労や高島市の関係者に望むこと等も聞かせてもらうことができました。
退院前カンファレンスの開催はリモートでの実施で大津市と高島市の距離や時間を短縮できます。ターミナルで退院される場合や外来では、充分に支援できていない場合もあるということで、どのようにバトンを渡していくか、タイミングや連携してつないでいくことにまだ課題もあり、お互いがどこまでできて、どこができていないかを明確にして連携できるとよい。地域のネットワークや顔の見える関係の大切さを再認識できた良い機会をいただくことができました。
今後も各関係機関が役割を発揮し、さらに連携を深めていきたいと思います。






◆次回の予定 第160回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
令和7年度 多職種連携セミナー
日時:令和8年 2月 14日(土)15:00~17:00
会場:今津サンブリッジホテル サンブリッジホール
内容:講演 「総合診療医の養成と在宅医療 ~竜王町で行っていること~」
講師 雨森 正記先生
医療法人滋賀家庭医療学センタ― 弓削メディカルクリニック 理事長
一般社団法人滋賀県医師会 理事
日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県支部 支部長
「在宅療養講演会」を開催しました
日 時 令和7年12月13日(土) 午後2時~3時45分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 「落語で笑って学ぼう!笑ンディングノート」
創作落語 「天国からの手紙」
講 演 「エンディングノートについて」
講 師:生島 清美 氏
行政書士 ・ 社会人落語家 天神亭 きよ美
参加者 106名
行政書士であり、社会人落語家として活動されている生島清身先生をお迎えして、エンディングノートに関する落語と講演会を行いました。
「天国からの手紙」は、生島先生が創作されたオリジナルの落語で、最期を迎えたお母さんが天国の案内人に、遺産相続や遺言書が必要なこと等を教えてもらいます。あの世とこの世・・ユーモアを交えながら大変わかりやすく、相続や看取り等についての考えを家族等に伝えることが必要なことを教えていただきました。
講演でも、遺言や相続、エンディングノートについて、わかりやすく教えていただくことができました。
相続は争いのもとになります。「きっとこう思っているはず」は、自分勝手な想像でしかありません。思いを書いておくこと、伝えておくことで無用な争いは起きなくなります。
エンディングノートは、これからをどのように生きるか、自分の人生をデザインすることが大事で、ポジテイブなものです。また、家族や周りの人に思いを伝えるために書くことが大切です。伝えたいことは、ことばにしなければ伝わらないということです。
エンディングノートを暗いイメージでとられえられていた皆さんでしたが、プラスのイメージに変わったという感想をたくさんいただくことができました。
・終活というより、今をより良く生きるために重要なノートになりそうだと思います。
・暗いイメージでなく、これからどのように生ききるかということに重きを置いてみる。
・自分の思いを家族に伝えるようにしようと思う(言葉にすることの大切さ)
・落語にてわかりやすく、死後の様子が想像できて用意する決心が出来ました。



「たかしまマイウェイノート」
自分らしいこれからの生き方や自分の思いを書いていきましょう
大切な人たちへ自分の思いをことばにして伝えていきましょう
市民の皆さん ひとり一人が自分らしい生き方 “マイウェイ” を描いて
ノートを使っていただけることを願って、今後もさらに啓発に努めます
「たかしまマイウェイノート」について 出前講座を実施しています
ご希望の方は、ぜひご連絡ください
第158回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和7年12月11日(木) 午後2時~3時15分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「認知症施策とチームオレンジについて」
話題提供者 高島市 健康福祉部 高齢者支援課 保健師 多胡 章子 氏
チームオレンジ「はぴねすマキノ」 田中 千賀代 氏
今回は「認知症施策とチームオレンジについて」と題して、高島市高齢者支援課とチームオレンジ「はぴねすマキノ」より話題提供していただきました。
はじめに、高島市高齢者支援課より、要介護認定の状況や認知症基本計画、高島市チームオレンジの活動等について話していただきました。
要介護認定の原因疾患の第1位が認知症で、4分の1を占めます。基本計画では、認知症の人と家族を支える体制づくりとして、7つの具体的な取り組みが推進されています。
その中の大きな柱が「新しい認知症観」を理解していることで、「(症状が出ても)できることややりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら自分らしく暮らし続けることができる」ということです。
高島市チームオレンジは令和6年度に設置され、現在5団体が認定されてボランティアとして活動されています。
次いで、チームオレンジ「はぴねすマキノ」より、はぴねすカフェの活動を紹介していただきました。“人と会う機会として” “居場所として” “つながりを求めて” 地域の誰もが困った時に話を聞いてもらえる場所として解放されています。誰かと話したい方、物忘れが気になる方、介護をされている方等、気軽に立ち寄れる場所となっています。
また、認知症のニーズ調査では、「主治医が往診してくれて、専門医につなげてくれた」や「家族の介護は嫌がるが、ヘルパーは受け入れられていた」「最初はずいぶんショックを受けた。患者に対する支援をもっとしてほしい。心細く思う」等の声があったということです。
意見交換では、新しい認知症観に変えるきっかけは何か、今後必要な支援や課題等について話し合いました。
認知症の正しい理解が広まることが何より大切で、小さな時から家庭でも、企業等でも学習する機会が必要である。病気としての認識や家族会や同じ立場にある人からの声かけ、お互い様の精神、誰でもどこでも手を差しのべられる地域づくり等の必要性が話題になり、参加者全員で共有することができました。
認知症になっても、誰もが自分らしく暮らしつづけることができる高島市を目指して、専門職自身も研鑽を積み、連携して取り組み続けることが必要なことであると再認識しました。



◆次回の予定 第159回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和8年1月15日(木)14:00~15:15
会場:安曇川公民館 ふじのきホール
内容:話題提供 「大津圏域と湖西圏域間の連携の現状や課題および今後の展望等」(仮)
話題提供者 大津赤十字病院
副院長・患者支援センター長 片倉 浩理 先生
医療社会事業部 地域医療連携課長 長谷川 豊 氏
医療社会事業部 総合医療相談室長 梶原 英輝 氏
第157回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和7年11月6日(木) 午後2時~3時15分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「“DNAR” ~命の現場と意思決定~」
話題提供者 高島市消防本部 警防課
救急救命士 兼田 知育氏
今回は「“DNAR” ~命の現場と意思決定~」と題して、高島市消防本部より話題提供していただきました。
はじめに高島市消防本部について説明がありました。職員は102名そのうち救急救命士は36名が活動されています。救急に関する課題では救急車の適正利用等もありますが、今回は“DNARへの対応”に焦点を当ててお話していただきました。
“DNAR”とは、「患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわないこと」です。
心肺停止で救急車が到着しても、蘇生を拒否されるケースが2割もあるということで、救急隊は対応に苦慮されています。
法律では、救急隊は傷病者を適切な病院へ搬送しなければならないと規定されており、生命が危険な方の救急救命処置が任務です。救急車を呼ぶということは、「あらゆる手段を使って全力で命を救ってほしい!」ということで、それに応えるのが使命です。救急隊の任務と“DNARは、相反する部分があるということになります。不搬送とするのは、明らかに死亡している場合や医師が死亡していると判断した場合のみとなります。
対応に苦慮した事例では、「施設からの救急要請で施設へ到着。DNARが不明であるため心肺蘇生を継続し救急車内に傷病者を収容したところ、DNARが確認でき、かかりつけ医を呼ぶこととなり心肺蘇生を中止した。」ということがありました。
意見交換では、地域ごとの各グループに各部署に配属されている救急救命士さん等の消防職員さんが6名も入っていただくことができ、下記の内容について大変有意義な意見交換ができました。
・意思表示の書類は毎年更新しているの?
・口頭のみで書類がない場合は、処置をするべきなの?
・突発的な事故での心肺停止はDNARの適応となるの?
・DNARの方へ心肺蘇生法を実施すべきなの?
・DNARの方を看取る体制はあるの?
多職種が様々な事例や場面での経験や実態から、活発な意見交換ができ、お互いの現場を理解し共有することができました。
DNARの意思表示をしていても、家族の気持ちが揺れ動き、心肺蘇生を希望されることがあります。それぞれの立場での課題や悩み等を共有することができました。命のバトンの活用やACP、「たかしまマイウイェイノート」の普及等、多機関、多職種で意見交換し、ルールづくりが必要なこともわかりました。
本人の意思が尊重され、意思決定支援を行う多職種のチームで、今後も取り組んでいくことが必要な大切なことであると確認でき、その一歩になる機会となったのではないかと思います。



◆次回の予定 第158回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和7年12月11日(木)14:00~15:15
会場:安曇川公民館 ふじのきホール
内容:話題提供 「認知症施策とチームオレンジについて」(仮)
話題提供者 高島市 高齢者支援課 保健師 多胡 章子氏
チームオレンジ「はぴねすマキノ」
第156回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和7年10月2日(木) 午後2時~3時15分
場 所 新旭公民館 多目的ホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「歯の歯式と高齢者のむし歯の成り立ち、義歯の種類」
話題提供者 高島市歯科医師会
原田歯科医院
院長 原田 直一先生
今回は「歯の歯式と高齢者のむし歯の成り立ち、義歯の種類」と題して、原田歯科医院の原田先生より話題提供していただきました。
歯の構造やむし歯になる原因、過程等、一つひとつわかりやすく教えていただくことができました。
食事をすると口の中が酸性になり、Caなどのミネラルが溶け出してむし歯となっていきます。口の中は、唾液で守られているが、高齢者になると多いむし歯、歯の喪失は、唾液の減少や乾燥、咬耗摩耗によって歯が欠けてしまうこと、歯周病により歯肉退縮が起きることが原因となっています。
義歯には2種類あり、歯が全部ない人には無歯顎(フルデンチャー)、部分的にない人には有歯顎(パーシャルデンチャー)が使われる。
全部の歯がない場合でも、歯を残している場合がある。歯根膜があり、噛んでいるという受容が脳に伝わっている。しかし歯がなくて粘膜で噛むと脳に刺激が行かないため、少しでも歯があった方がよい。噛むことは認知症の予防にもなるということです。
意見交換では、原田先生にもグループに入っていただき、質問に多数答えていただきました。
・義歯をはめているか、はめていないかでも認知症の進行が変わるというデータがあり、合った義歯で食事
をすることが大切
・歯は摩耗するので、歯の磨き方、磨く力も大切
・食べたらすぐに磨くこと、最低でも唾液の循環がなくなる寝る前には歯磨きをすることが大切
・口腔内の乾燥が目立つ時には、唾液の分泌を促す唾液腺マッサージをするとよい。口腔体操もある。
・関わっている高齢者で、歯科受診をされている方は無いに等しい。食事面で困りごとがなければ、口腔に
関することがおろそかになっている。
・子どもの頃は定期的に歯科検診があるが、成人になるとなかなか無い。40歳・50歳の歯周病検診が実施
されているが、受診率はかなり低い。
歯や口腔に関しては、参加者自身も知識や関心がまだまだ浅く、痛みが出てからしか受診しないことも多くあります。また、昔に聞いて正しいと思い込んでいることが、最新の研究では変わってきていることもありました。治療や予防に関すること等、最新の知識を一緒に学んで伝えていくことの大切さを再確認しました。
市民の皆さん、自分自身も含めて、歯を生涯にわたり大切にしていくために、予防や受診行動につながるように支援していきたいと思います。



◆次回の予定 第157回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和7年11月6日(木)14:00~15:15
会場:安曇川公民館 ふじのきホール
内容:話題提供 「“DNAR” ~命の現場と意思決定~」
話題提供者 高島市消防本部 警防課
救急救命士 兼田 知育氏
*各所属から、救急救命士、消防職員の方が参加してくださいます
「たかしまマイウェイノート」を “書いて良かった”
「たかしまマイウェイノート」に関するアンケートを実施しました。集計途中の結果を一部報告します。
目 的:「たかしまマイウェイノート」をより良いものとし、市民ひとり一人が望む暮らしを描いて活用
できるよう、意見や感想等をまとめて、内容の検討や普及を行う資料とする
方 法:郵送アンケート
対象者:「たかしまマイウェイノート」を持っている人
令和6年度の講演会等に参加し、住所・氏名を記載してノートを持ち帰られた方に郵送(133人)
令和7年7月より窓口等で配布するノートには、アンケート用紙を封入
期 間:令和7年7月より
結 果:回収数 40(令和7年9月22日現在)
集計途中の概要は、PDFファイルのとおり(こちらからご参照ください)
「ノートを書いて良かった」
という声を たくさんいただきました!
【アンケート結果から】 一部抜粋
・ノートを活用することで、自分の思いや考えを伝えることができると思う 約97%
・ノートを書いて良かったと思う 100%
・「人生の最終段階の医療やケア」に関する思いを 伝えている 約30%、 伝えていない 約30%
今後伝えたい 約30%
・ノートを書いた人(書きたいところのみ、記入の途中)約40%、今後記入しようと思う 約50%
【アンケートを返信していただいた方の声】
・残された人生において、まだやり終えてない事を見つけられたので、それを達成すべく今まで以上に
心のエンジンが回転しだした。
・これから残された時間を意義あるものにするために、自分で思いを文にするのは良い事と思う。
・60代も後半になると家の中も片づけ、いずれ来るであろう死というものに、なるだけ迷惑をかけない
よう生き方、話し合い、記憶ではなく記録が大事と思います。
・終末医療をどうするか、認知症になったら自分の意思をどう伝えるべきか、こんなことに活用できる
ノートだと思うので、今後前向きに取り組みたいです。
・遠方に住む一人暮らしの義兄が倒れ命は取りとめましたが、意思の疎通ができず、各種支払いや病院の
事など、ずい分困った事になり大変でしたので、自分はそんな事のない様にと、必要と思われる事を
書き残しておく為に、「マイウイェイノート」は、ありがたいと思い活用しています。
〇ノートは持っているが、活用している人はまだ少ない
〇ノートを書いた人は「良かった」と思っている 100%
🍀ノートは使っていただくと、良さがわかります
🍀書きたいところから書いてみてください
🍀あなたのこれからの人生を豊かにできるノートです
<お願い>
アンケート用紙をお持ちで回答がまだの方は、ぜひ送付をお願いします。
アンケート用紙がない方は、事務局へご連絡ください。
あなたの思い、ご意見を聞かせてください。
第155回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和7年9月4日(木) 午後2時~3時15分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「在宅における排尿支援
~機能性尿失禁への看護のポイント~」
話題提供者 高島市民病院
皮膚・排泄ケア特定認定看護師 荒川 貴一氏
今回は「在宅における排尿支援~機能性尿失禁への看護のポイント~」について、高島市民病院の皮膚・排泄ケア特定認定看護師より話題提供していただきました。
尿が漏れたり、間に合わない、出ないのに何度もトイレへ行く、おむつを外してしまう等、排尿に関する困りごとはたくさんあり、それは毎日何度も続いたりします。
こういった悩みにどのように対応するとよいのか。尿失禁の種類や原因、環境等と合わせて、ケアや対策を考えていくことが大切で、一つひとつ方法や工夫を教えていただくことができました。
意見交換では、薬との関連や排尿のパターンが掴みきれない等の悩みが話されました。
うまくいったことでは、廊下で排尿をされる人があり、ガラスに鳥の写真を貼ったらその行為がなくなったという事例がありました。一人一人に合わせて日々工夫されていることがわかりました。
最後に講師より 排尿支援を行う際の心構え
・加齢により今までできていたことができなくなる 他人の手を借りることになる
自尊心の低下や負い目を感じてしまっていることを介助者は認識しておく
・排尿支援はプライバシーに深く関与する
・介助者がよいと思う方法を本人が受け入れないこともある
・尿失禁そのものだけでなく、尿失禁をしないように生活を制限していることもQOLを低下させている
・尿失禁ありきの排泄管理が本人にあたっているなら、それをサポートするのも排泄支援
目指すのは、「その人の生活に合った排泄管理」
本人の意向や生活様式を捉えながら、その人に合った方法を探していきましょう!
排泄に関しては、プライバシーがあり恥ずかしく、できれば最期まで自立できることを誰もが願うことですが、その思いを忘れずにケアしていきたいと思います。
排泄という特定の看護分野における高度な知識と技術をもつスペシャリストとして、地域で頼れる心強い存在が増えました。本人の悩みはもちろん、看護や介護をする人たちの困りごとを解決できるよう、今後も排泄に関する相談や支援を広げていただけると嬉しいです。
そして、誰もが気持ちよく排泄できることで、さらにQOLの維持向上ができるよう予防や医療、介護の連携がすすむように取り組んでいきたいと思います。



◆次回の予定 第156回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和7年10月2日(木)14:00~15:15
会場:高島市観光物産プラザ (新旭公民館) 多目的ホール *会場を変更しています
内容:話題提供 「歯の歯式と高齢者の虫歯の成り立ち、義歯の種類」
話題提供者 高島市歯科医師会
原田歯科医院 院長
歯科医師 原田 直一先生
「在宅医療」の出前講座で 地域へ出かけています
日 時 令和7年8月7日(木) 午後2時~3時
場 所 黒谷区 会議所
内 容 ふれあいサロン
講演:「在宅医療」って何?
講師:松本 道明先生
高島市医師会 会長 ・ まつもと整形外科 院長
今回は、黒谷区のふれあいサロンでの 出前講座の様子をお伝えします。
高島市医師会 会長の松本先生より、「在宅医療」についてのお話をしていただきました。
地域から要望のあったテーマに沿って、在宅医療とはどういうものか、どうしたら受けられるのか、高島市での在宅医療の現状や相談機関等についても、くわしくお話を伺いました。
参加された皆さんは、医療や介護の実態、医療のかかり方等、うなづきながら熱心に耳を傾けておられました。
在宅医療の利点や方法を知ることができ、高島市では最期まで安心して家で治療を受けながら、暮らしていくことができることがわかり、在宅医療を選択肢として考えられる機会となりました。
皆さんからの質問にも丁寧に答えていただき、家での転倒の注意点や痛みの対処、診療所にかかることのメリット等も知ることができました。
また、治療や検査、病気との向き合い方、これからの生き方等について、先生としっかりと相談し、説明を受けて考えていくことの大切さ学びました。


黒谷区のふれあいサロンでは、他に健康推進員さんから「減塩とフレイル予防」のお話や体操の実践、減塩の「つや玉トマト」の試食等があり、福祉推進員さんからは地域の高齢化率の実態や要介護となる主な原因、住民福祉計画等のお話もありました。盛りだくさんのお話でしたが、「たかしまマイウイェイノート」についても、ご紹介させていただきました。
地域の皆さんが元気で過ごせるよう、また誰一人取り残さない地域にと、地域も医療や介護、福祉、保健の関係者等も、皆が力を合わせいけるように取り組んでいきたいと思います。
出前講座は、市民の皆さんと医師等が、膝を突き合わせてお話できる機会です。
ご希望があればお伺いします。ご連絡をお待ちしています。
第154回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 令和7年7月3日(木) 午後2時~3時15分
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 話題提供と意見交換
話題提供 「地域の中で助け合えるまちづくり」
話題提供者 特定非営利活動法人 元気な仲間
代表 谷 仙一郎 氏
今回は「地域の中で助け合えるまちづくり」について、元気な仲間より話題提供していただきました。
地域、そしてそこで暮らす人々、仲間への熱いあたたかな想いを聴かせていただき、参加者全員が元気をいただくことができました。
これから高齢化、人口減少等にどう対応していくのか、自分たちの老後はどうなるのかと先を見据えた時、自分たちでできることをしていこう、そして持続可能な形が必要、自分の老後も住みやすいまちにということで平成15年にNPO法人を立ち上げられました。
「住み慣れた地域の中で、その人らしい普通のくらしを」をモットーに介護保険事業だけでなく、制度に関係なく集い、活動できる場は多岐に渡ります。普通の民家を改修し地域の中に溶け込んだデイサービスや買い物支援、居場所づくりなど、住民が支えあえる地域づくりを目指して活動は広がっています。
デイサービスや小規模多機能でも、誰もが役割をもって活動し、その人の希望を叶え、できることをして過ごされ、最期の時まで支援されています。実の家に帰っても「早くここへ帰りたい」と言われるほど、安心して落ち着ける自分の家になっている様子も聞かせていただきました。
有償ボランティア「たすけあい高島」は、困りごとを助け合うお互いさまの取り組みです。労働の対価としてではなく、感謝の気持ちとして支払われます。その活動の中で、93歳にして一人暮らしデビューをされた方もあったと、ちょっと嬉しい絆のエピソードも聞かせていただきました。
会員さんは「人から何かをしてもらった時も幸せ」だけれど、「自分が人の役に立てたと感じられる時が幸せ」と、自分の役割や意義を実感できる機会として活動を続けられています。
たすけあい活動は、できることをできる人ができる時にすること
相手の事を想ってする活動
なにより活動者の生きがいにもつながります
「きょういく」と「きょうよう」が大事
今日行く(きょういく)ところがある ・ 今日すべき用事が(きょうよう)がある
これを実現するために、地域の居場所づくりや役割づくりが大事となります。そして、担い手として高齢者が社会参加していくことが必要です。
意見交換では
・高島市に「谷さんは何人いるんだろう ミッキーマウスのよう」
・介護保険サービスではまかないきれないサービスの仕組みがある
・理想的な活動をされている。元気な高齢者とも交流できる、高齢者が働ける場がある
・NPO法人の立上げの講習会を開いて欲しい・・・谷さんより「お手伝いしますよ」
・続けていく力、巻き込む力、人の力を引き出す力がすごい
・自分たちの老後がどんなまちだったらいいのか、住みやすいまちはどんなまちか、気になる人を増やして
いきたいという想いが浸透するとよい
最後に谷さんより、制度から外れていく人は必ずいるので、他の人を気にかける住民が高島市の中で増えていくといい。究極は「たすけあい高島」がなくても、普通にたすけあいがあるという地域になることが目標ですと伺いました。
市民のみんなの力で、できることをできる人ができる時にすることで、普通に暮らしやすい高島市となることを一緒に目指していきたいと思いました。



◆次回の予定 第155回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時:令和7年9月4日(木)14:00~15:15
会場:安曇川公民館 ふじのきホール
内容:話題提供 「排泄支援について ~ケアで改善できます~」(仮)
話題提供者 高島市民病院
皮膚・排泄ケア認定看護師 荒川 貴一氏
*8月は休会となります