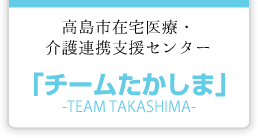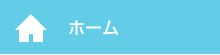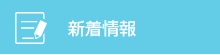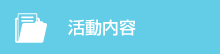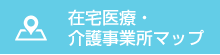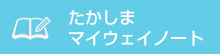新着情報
カテゴリー「報告」の記事
「高島の在宅医療を考える会」を開催しました
日 時 令和元年6月12日(水)午後2時~3時30分
場 所 今津病院 会議室
テーマ ~在宅療養を支える「レスパイト入院」について考える~
参加者 63名
今回は、第94回高島市医療連携ネットワーク運営協議会と合同で開催しました。
前半は今津病院の地域連携室 竹本正樹氏、マキノ病院入退院支援室 山本暁氏、高島市民病院 地域医療連携室長 末武美里氏よりレスパイト入院の意味や各病院の利用者数や利用者の特徴、課題などについて報告されました。
後半は4つのグループに分かれ、意見交換を行いました。
レスパイト入院の体制が整備されたことにより、これまで介護施設でのショートステイが難しかった医療依存度の高い方や、透析患者、小児の受け入れが可能になってきたことは、在宅療養中の患者や家族にとって、大きな支えの一つになっていることがわかりました。また、在宅療養の中で、摂食・嚥下やリハビリに関する再評価の機会としても受け入れが可能ということで、在宅での療養生活を安心しておくる一助となっていることがうかがえました。
一方、今後の課題として「ケアマネとしても、レスパイト入院とショートステイの違いを正しく理解して相談していく必要がある。」といった意見のほか、レスパイト入院の周知や相談窓口の明確化を求める意見も出ていました。他にも「医療処置などの必要な利用者については災害時の対応を前もって確認しておくことも大事。」など活発に意見交換が行われました。


◆次回の予定
〇7月10日(水) 午後2時~3時
場所 今津老人福祉センター
内容 話題提供 高島市消防本部より
第93回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました。
日 時 令和元年5月8日(水) 午後2時~3時
場 所 今津老人福祉センター ホール
参加者 38名
内 容 話題提供『小児領域人材育成研修会の取り組み』
提供者 高島市リハビリ連携協議会 会長 船木 廣子氏
今回は、高島市リハビリ連携協議会から、昨年度からの新たな取り組みについてお話していただきました。
高島市内において、小児在宅ケア児に対するリハビリ専門職の関わりのニーズが高まってきていることから、小児領域にも対応できるリハビリ専門職を育成するため、改めて基礎から勉強しようと研修会の実施に取り組まれたとのことでした。24名の受講者のうち、11名が今年度から新たに同協議会の小児部員として活動されるそうです。
また同協議会では、市からの人材派遣の要請に対応したり、地域サロンの運営にリハ職としてどう関わるか検討するなど、専門職として地域との関わりを着実に展開しておられる活動についてわかりやすくお話してくださいました。
グループワークの中からは、「今はまだ、小児に対しての連携体制はできていない。」「訪問看護が抱え込んでいる?」「訪問リハビリでは、作業療法士や言語聴覚士の訪問の希望も出てきている。」「在宅では、生活にリンクしたリハビリをしていくことが必要。」「人の集まるサロンなどにリハビリ職の方が来てくれるのはよい。」など、リハビリ職の今後の活動に期待する意見がたくさん出ていました。


◆次回の予定
〇6月12日(水)午後2時~3時30分
場所 今津病院 2階 会議室
内容 「高島の在宅医療を考える会」として開催
テーマ ”在宅医療を支える「レスパイト入院」について考える”
第92回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 平成31年4月10日(水) 午後2時~3時
場 所 今津老人福祉センター ホール
参加者 41名
内 容 話題提供「薬剤師の仕事紹介」
提供者 高島市薬剤師会 会長 田中 聡美 氏
今月は、高島市薬剤師会より地域の薬剤師さんの業務についてご紹介していただきました。地域の薬局において、薬剤師さんは、処方箋による調剤や処方だけでなく、患者さんの困りごとに対してこまかな工夫やアドバイス、主治医への提案など様々な役割を担っていただいていることをお話いただきました。また、在宅への訪問薬剤指導を行う薬局も増えていることがわかりました。
さらに、最近はがんを患う患者さんも増えていることから、医療用麻薬の取り扱い上の注意点などについてもお話してくださいました。
後半は、薬剤師会の発表をもとにグループに別れ、薬剤師さんへの質問や期待することなどが話し合われました。
グループワークの中では、「薬剤師さんの仕事がよくわかった」「薬の管理は訪問薬剤師さんのおかげでよくなってきた」などの声がある一方、「病院の薬剤師さんと地域の薬剤師さんの連携はどうか?」「どういう人を薬剤師の訪問につなげたらいいかわからない」などの意見も出ていました。また、災害時や特殊な薬の確保などの観点から「薬や衛生材料などがどこにあるのか見える化することができるとよい」といった意見も出るなど、今後に向けて貴重な意見交換の機会となりました。


◆次回の予定
〇5月8日(水) 午後2時~3時
場所 今津老人福祉センター
内容 話題提供 高島市リハビリ連携協議会より
第91回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 平成31年3月13日(水) 午後2時~3時
場 所 安曇川公民館 カルチャールーム
参加者 18名
内 容 話題提供「平成30年度高島市在宅医療・介護連携推進事業について」
提供者 高島市医師会在宅療養支援センター コーディネーター 清水 文枝
今回は、高島市医師会在宅療養支援センターより、平成30年度の在宅医療・介護連携推進事業の実施結果について報告させていただき、次年度に向けて参加者の皆様からご意見をいただきました。
医療・介護の連携事業については、顔の見える関係づくりから職種間の連携がすすむ中、リハビリ連携協議会と介護支援専門員連絡協議会の自主的な合同研修が開催されたり、訪問看護と歯科医師や薬剤師との連携などさまざまな職種間で個別支援を通じた連携がすすんできています。
在宅療養支援センターに対しては、「地域連携パス」の活用について病院から地域へのスムーズな引継ぎができるよう協力してもらいたい、とのご意見や、在宅療養支援センターの事務所が高島市民病院内にあることや「地域医療連携推進法人」とも同一事務所内にあるというメリットを生かして、シームレスな連携ができるよう活動してほしい、とのご意見もいただきました。
また、あさがおネットの活用については、高島での効果的な活用事例などをもっと市外にもアピールしていく役割もあるのでは、とのご意見もいただくなど今後に向けて貴重な機会となりました。
今後とも在宅医療や介護に携わる方々の連携相談窓口として、気軽に声をかけていただけるよう活動してまいります。(清水文枝)


◆次回の予定
〇4月10日(水)午後2時~3時
場所 今津老人福祉センター
内容 話題提供 高島市薬剤師会より
多職種連携セミナーⅡ(第90回高島市医療連携ネットワーク運営協議会)を開催しました
日 時 平成31年2月16日(土) 午後2時~4時30分
場 所 寿光苑
参加者 47名
内 容 テーマ「褥創ケアはおもしろい~チームワークで褥創を考える~」
〇講演「チームワークで褥創ケアを考える」
講師 マキノ病院 皮膚科 片岡照貴 先生
〇ミニレクチャー「褥創ケアの最新情報」
講師 高島市民病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 伊庭治代 氏
今年度2回目の多職種連携セミナーは、「褥創」をテーマに、講義とグループワークの2部構成で行われました。
片岡先生からは、褥創発症のリスクアセスメントから褥創ができてしまった場合の診断や治癒の経過、治療についてわかりやすくお話をしていただきました。そして、急性憎悪期の褥創のほか、壊死や発熱を伴う褥創は入院治療を要するが、それ以外は、基本的にこれからは在宅で治す疾患である、と説明されました。そのためには、まずは、よく観察してアセスメントすること、徐圧と適度な湿潤環境を保つこと、医師、看護師、リハビリ職、栄養士など多職種がチームで関わることが大事であると結ばれました。
伊庭看護師さんからは、褥創の状態に応じたケアについて、褥創の局所のケアを始め、体圧分散の管理、ポジショニングなど最新情報を交えながら具体的にお話して下さいました。
講義の後、6つのグループに別れ、多職種で褥創発生の要因についてアセスメントし、今後必要と思われる支援について検討しました。そして、最後には、各グループの話し合い結果を発表し、参加者全員で共有しました。


◆次回の予定
第91回高島市医療連携ネットワーク運営協議会
日時 平成31年3月13日(水) 午後2時~3時
場所 安曇川公民館 ふじのきホール
内容 話題提供 高島市医師会 在宅療養支援センターより
第89回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 平成31年1月9日(水) 午後2時~3時
場 所 今津老人福祉センター
参加者 35名
内 容 話題提供 「災害時リスクアセスメントシートを活用した支援事例」
提供者 湖西介護支援専門員連絡協議会 会長 澤田 悦子氏
ケアプランさくら 介護支援専門員 武長 幸子氏
今月は、湖西介護支援専門員連絡協議会から、事例をご紹介いただき、災害時の支援における課題などについて意見交換を行ないました。
湖西介護支援専門員連絡協議会では、昨年度災害時における個別支援プランの作成に関する勉強会を実施され、それをきっかけに、自事業所でもリスクアセスメントシートを活用した要援護者の整理や支援方法の確認などの取り組みを始めておられるとのことでした。その中で、昨年の台風時に対応された事例を紹介されました。そして話題提供の後、参加者で4グループに分かれて意見交換を行いました。
意見交換の中では、ケアマネからは、「寝たきりなど避難が難しい利用者で、事前に予測できる場合はショートステイの利用やレスパイト入院の調整を行うが、地震の場合などは対応が難しい。」「避難所までの移動手段なども本人や家族と話し合っておく必要がある。」また、訪問看護の方からは、「普段寝ている場所が安全であるかの確認も必要。」「人工呼吸器などの予備電源の確保はどうするのか、など家族にもあらかじめどこに相談するかなど話しておくことが大事。」などの意見も出ていました。実際に市内の病院では、昨年の台風時には、人工呼吸器の方や透析の方のレスパイト入院も受入れされていたようでした。
その他避難所に関しても、「移動しにくい人が避難するので福祉避難所は早めに開設してほしい。」などの要望や「介助の必要な方も家族がまとまって避難することで避難先で家族が対応できるのでは。」などの意見も出ました。
また、「災害時要援護者に登録している利用者でも、本人の状態は変化するので、たとえば、退院時カンファレンスの時などに、災害時の対応の確認が出来るとよい。」などの意見も出ていました。
災害は、いつ、どのような形で起こるかわからない中、いざと言う時、まずは「自助」、自分で自分の身を守ると言う意識をみんなが持つことが大事、その上で、何が出来て何に手助けが必要なのか、について本人、家族を含めてアセスメントをしておくことが大切であることをどのグループでも確認していました。


◆次回の予定
第90回高島市医療連携ネットワーク運営協議会は「平成30年度在宅医療多職種連携セミナーⅡ」
と合同開催になります。
日時 平成31年2月16日(土) 午後2時~4時30分
場所 寿光苑 (高島市安曇川町青柳1472)
「高島地域歯科保健推進研修会」~口腔機能向上に向けた施設研修~を開催しました(高島保健所)
高島市は、高齢化率が34.6%(平成30年10月1日現在)と県内でも最も高い状況にあります。生涯を通じておいしく食事をするためには、口腔内の健康が大切であり、日ごろの口腔ケアの充実を強化していく必要があります。そこで保健所では、今年度から、介護サービス事業所に勤務する職員や地域の歯科衛生士を対象に、口腔機能の維持・向上および技術の向上を図り、サービス利用者の特性に応じた口腔ケアが実施できるよう、研修会を企画しました。
今回は、その第1回目として、地域の歯科医師、歯科衛生士・高島市の協力により、「デイサービスほたるの苑」において、昨年10月4日と11月1日の計2回の研修を実施し、利用者の口腔アセスメントに基づいた指導を行いました。
《研修に参加された施設の方からの感想》
・義歯を作られ調整に時間をかけてもうまく合わず、結局、義歯なしで食事される利用者さんや、歯が痛くてもすぐに歯科受診に結びつかない利用者さん等、日頃から口腔ケアに対して問題を抱えていたところ、このような研修の機会を与えていただきました。
・家族さんには事前にアンケートやチェックリストの記入にご協力いただき、研修会の終わりに、担当歯科衛生士さんから「よかった点」「気になる点」としてまとめたものをお渡しすることが出来てよかったと思います。その後、歯科受診され、義歯の状態が改善した方や、歯痛の原因が明らかになった方などがありました。これは、利用者さんや職員双方にわたり丁寧にご指導いただいたたまものです。
・毎年6月に市の健康推進課から歯科衛生士さんに来ていただき、食事前の”口の体操”の指導もしていただいていますが、今回の研修でこの体操の大切さを再確認できました。
・職員に対してのミニ講義で、口腔ケアで大切なことは、歯磨き、義歯の手入れ、および舌の清掃をすることと学びました。また、全体を通して「いつまでも美味しく安全に食べる」という言葉が印象に残りました。




「高島まるごと介護予防まつり」(兼第88回高島市医療連携ネットワーク運営協議会)が開催されました
去る12月2日(日) 午後から、安曇川公民館において、「高島まるごと介護予防まつり」が開催され、171名の方が参加されました。
今年は、「笑って、学んで、健口になろう」ということで、お口の健康をテーマに開催されました。
ふじのきホールでは、滋賀県歯科医師会常務理事の大西啓之先生の講演をはじめ、高島あしたの体操や笑いヨガの体験コーナーが設けられ、ロビーでは、高島市リハビリ連携協議会やたかしま福祉用具の会の展示や体験コーナーが設けられました。また、看護協会による「まちの保健室」での健康チェックや福祉用具ボランティア「ほほえみ工房」による自助具の展示などもありました。
2階では、歯科医師会による相談コーナーやお口元気アップコーナー、栄養士さんによるやさしい介護食教室などのコーナーが設けられ、参加者らはそれぞれ関心のあるコーナーを回り、見て、触れて、体験しながら、食べることの大切さやお口の健康についても考える機会となりました。子どもたちもスタンプラリーに挑戦し、笑顔で景品を受け取っていました。
参加者からは「お口の話はわかりやすく楽しく聞け、実践したい。」体験コーナーも「いろいろ体験できてよかった」「介護食は帰って作ってみます」など喜びの感想がたくさん寄せられました。


大西先生の楽しいお話 高島あしたの体操を体験


会場(1階)の様子 お口元気アップコーナー
多職種連携セミナーⅠ(第87回高島市医療連携ネットワーク運営協議会)を開催しました
日 時 平成30年11月8日(木)午後2時30分~4時
場 所 安曇川公民館 ふじのきホール
内 容 テーマ:子どもから高齢者まで安心して生活できる地域づくり
講演「全世代型地域包括ケアへの挑戦」
講師 米原市地域包括医療福祉センター「ふくしあ」
センター長 中村 泰之 氏
今回は、高島市と高島市医療連携ネットワーク運営協議会の共同開催となりました。
最初に、米原市地域包括医療福祉センター「ふくしあ」の中村先生より、センターの成り立ちや現在の活動についてお話をしていただきました。「ふくしあ」では、現在、小児から高齢者までの在宅療養支援をはじめ、看取り、認知症初期集中支援、さらには若者の不登校、閉じこもりの方へのカウンセリングなども行なっておられると事例も交えてお話してくださいました。
また、「ふくしあ」は医療機関としての機能のほか、「地域包括支援センター」、「児童発達支援センター」、「病児保育室」などの機能も持っているため、医療、介護や福祉の関係機関だけでなく、教育関係の機関などとも連携しながら活動をされているということでした。そして今後は、さらに連携の範囲を拡大し、「ふくしあ」を小児から高齢者まで全世帯対応型の支援センターとして、地域の”ワンストップ窓口”にしていくことで、子どもも大人も障がいを持つ方もみんなが同じ場所にいて自然な形でいられる地域づくりをしていきたい、と締めくくられました。
講演の後は、「ふくしあ」の取り組みについて感じたことや、高島市ではどんな取り組みができるかなどについて意見交換を行い、参加者の交流を行いました。


〇次回の予定
・第88回高島市医療連携ネットワーク運営協議会は「介護予防まつり」と合同開催となります。
日時 平成30年12月2日(日) 午後1時~
場所 安曇川公民館
第86回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました
日 時 平成30年10月10日(水)午後2時~3時
場 所 今津老人福祉センター
内 容 話題提供「平成29年度しあわせアンケート」結果から
提供者 高島市役所 地域包括支援課 主監 古谷 靖子氏
今回は、平成29年度に市が実施された「在宅療養生活しあわせアンケート」の結果について市役所地域包括支援課から報告をいただき、参加者間で意見交換を行いました。
この調査は、療養生活を送っている本人や主介護者に主観的な幸福感について尋ねたもので、在宅で最後まで療養生活ができる人はしあわせと感じる度合いが高い傾向がある。また、主介護者の30%は「介護負担が重い」と感じており、特に、要介護2、3の人の主介護者は負担感が重いと感じている人が多く、主観的幸福感も低い傾向がある等の報告がありました。
報告を聞いた後、日ごろの仕事を通じて、本人や家族のしあわせ感を高めるためにはどんなことができるのか、についてグループワークを行いました。
医療従事者の方からは、在宅療養を希望する患者や家族に、医療従事者が病気の説明をしっかりすることで、不安感が取り除かれる、不安感を除けば、しあわせ度を上げられるのではないか。といった意見や、しあわせ度は主観的なもの、家族構成や経済状態などによっても個々に違う。連携も大事だが、各専門職の領域でやれることをしっかりすることが大事、などの意見が出ました。また、在宅看取りが増えていているが、死をタブー視しないで、「死」について話し、考える機会を地域で作っていくことも必要ではないか、という意見も出るなど、さまざまな角度から意見交換が行われました。